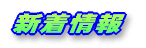
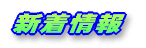
成年後見人制度」
四月一日から、介護保険制度とともに「成年後見制度」が発足した。精神上の障害で判断能力が劣った場合の「後見」について、従来の禁治産、準禁治産制度に代って、ノーマライゼーションの考え方に基づき法制化されたもので、高齢化社会を反映した制度である。
この後見人制度は、法定後見と任意後見の両制度からなり、法定後見制度は①後見、②保佐、③補助の三類型に分かれる。従来の禁治産、準禁治産の制度は、前記①後見と②保佐の制度に組み込まれた。また、①②に至らない判断能力の軽度の状況にある者に対する③補助制度が新設された。
法定後見制度は、被後見人の事理弁識能力の程度により前記①②③の類型の何れかを適用し、本人または関係者の申し立てによって家裁がそれぞれに見合った後見者を選任し、一定の権限を与えて本人に代わって、特定の法律行為ないし財産管理などの事務を行うものである。 また、「任意後見制度」は、本人が弁識能力のあるうちに任意後見者を指名しておき、その者に対し、後日「精神上の障害により、判断能力が不十分な状況に陥ったときに、自己の後見事務(生活、療養看護、財産管理に関する事務一の全部(一部)の代理権を与える」という委任契約による後見制度である。「任意後見法」に定められた制度であるにも拘わらず「任意」とされているのは、後見内容について当事者(本人と後見人)の任意の契約によるとされている由縁である。任意後見が法定後見と基本的に異なる点は、任意後見人の選任、後見内容が本人自身で決められるところにある。
今回の任意後見制度は、後見者の恣意的処理を防ぐため、公正証書による契約、契約の登記、家裁による「任意後見監督人」の選任が要件とされ、任意後見人の事務と任意後見監督人の役割が明確にされたことである。この規定と本人の意思が随所に盛り込まれたことにより、ノーマライゼーションを反映したものとなった。また後見人の複数の受任が可能となり、そうなれば「身上監護」は介護士が、「財産管理」は税理士がという図式が考えられる
税理士会新聞より6/9
1..任意後見制度の契約について
具体的に任意後見制度の契約について解説したいと思います。任意後見契約をする場合、本人との間で結ぶ契約によって、任意後見人の行う事務の内容は異なりますが、例えば、①金融機関との取引に関する事項、預貯金等の管理・払い出し、②不動産や大事な資産の財産管理・保存・処分、③遺産分割等の相続に関する事項、④賃貸借契約の締結・解除、⑤介護契約その他福祉サービス利用契約・医療契約の締結等が考えられます。また、任意後見契約は、公正証書によることが要件となっておりますので、私的な契約書は無効となります。公証人に支払う手数料は契約内容を問わず、通常は11,000円です。任意後見人を弁護士にした場合、事案により異なりますが、財産管理の基本手数料は、月30,000円程度、契約時に50,000円から20万円程度費用が発生するようです。任意後見人を親族にした場合は無償の契約もあり得ます。さらに、任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が本人の資力等を判断して、本人の財産の中から相当の額を定めることになっています。
2..成年後見登記制度
(1)成年後見登記制度とは
成年後見登記制度は、成年後見人などの権限や任意後見契約の内容などをコンピュータ・システムによって登記し、登記官が登記事項を証明した登記事項証岨書(登記されていないことの証明を含む)を発行することによって、登記情報を開示する制度で、東京法務局の後見登録課で全国の後見登記事務を取り扱っています。
(2)どんな時に登記をするのか
後見開始の審判がされたときや、任意後見契約の公正証書が作成されたときなどに、家庭裁判所または公証人の嘱託によって登記されます。また、登記されている本人・成年後見人などは、登記後の住所変更などにより登記内容に変更が生じたときは「変更の登記」を、本人の死亡などにより法定後見または任意後見が終了したときは「終了の登記」を申請する必要があります。この「変更の登記」「終了の登記」の申請は、本人の親族などの利害関係人も行うことができます。登記の申請は書留郵便で行います。
(3)どのようなときに登記事項証明書が利用できるのか
たとえば、成年後見人が、本人に代わって財産の売買・介護サービス提供契約などを締結するときに、取引相手に対し「登記事項証明書」を提示することによって、その権限などを確認してもらうという利用方法が考えられます。また、成年後見(法定後見・任意後見)を受けていない方は、自己が登記されていないことの証明書の交付を受けることができます。
(4)誰が登記亭項証明書の交付を請求できるのか
登記事項証明書の交付を請求できる方は、取引の安全の保護と本人のプライバシー保護の調和を図る観点から、登記されている本人、成年後見人など一定の方に限定されています。登記されている方以外の方で交付請求ができるのは、本人の配偶者、四親等内の親族などです。取引相手であることを理由に、請求はできません。
3.まとめ
任意後見制度と、法定後見制度では、任意後見の方が法定後見より原則として優先されます。ただし、任意後見契約が登記されている場合で、家庭裁判所は本人の利益のために特に必要があると認めた場合に限り、本人・配偶者・親族・任意後見監督人の申し立てにより任意後見契約を終了させることができます。超高齢化が進む現在において、ご自分のライフプランの検討課題、資産を有効に活用する相続対策として、また実際に痴呆等になったご家族を持つ当事者として、今後検討される余地のある制度であると思われます。大和証券資産管理読本7月より