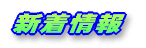
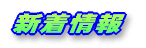
児童虐待の防止等に関する法律が成立....子供の権利を改めて見つめ直そう
5月17日「児童虐待の防止等に関する法律が成立し、24日公布、7月25日より施行される
この法律では、「学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健婦、弁護士その他児童の福祉に職務上関係ある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない」と定めました。併せて、守秘義務を面責する規定や、通告した者を特定特定させないための規定を盛り込んでいます。
児童虐待とは
○身体への外傷やそのおそれのある暴行、 ○わいせつな行為をしたり、させること ○著しい減食や放置等、監護を怠ること ○心理的外傷を与える言動と定義しています。
「病院に運び込まれた乳児が骨折していた。両親は『ベッドから落ちた』説明。診断した医師は、虐待があっがどうか確信が持てなかったので、そのまま自宅に帰して保健婦に後日、訪問してもらうことにした…」
児童福祉法では、保護を必要とする児童を発見した者は、福祉事務所または児童相談所に通告する義務があると定めています(二十五条)。五月十三日開かれたセミナー『親の暴力に傷ついた子どものケア』で、広岡智子さん(子どもの虐待防止センター)は、冒頭の事例を紹介しながら「疑いがあるときは、そのまま家に帰してしまってよいのだろうか」と問いかけました。
*児童虐待防止法への期待
5月17日、「児童虐待の防止等に関する法律」が全会一致で成立。この法律では、「学校の教職員、児童福祉爬設の職員、医師、保健婦、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない」と定めまし」。併せて、守泌義務を免責する規定や通告したものを特定させないための規定を盛り込んでいます。冒頭のように疑いのあるときには、積極的に通告されることを期待する法律です。
「法律で初めて、児童虐待を〈身体への外傷やそのおそれのある暴行〉〈わいせつな行為をしたり、させること〉〈著しい減食や放置等、監護を怠ること〉〈心理的外傷を与える言動〉と定義して、虐待を禁止する規定を位置づけた意義は大きい」と広岡さん。また、「『関係機関及び民間団体の連携』を法律に盛り込み、民間を含めたネットワークの必要性をうたっている」と評価しました。
*虐待を受けた子どものケアのために
発見や通告が増えるだけでは解決できないこともあります。参議院の附帯決議は、「児童相談所の体制と専門職員の資質の向上」を求めました。通告を受けた児童相談所が十分にその役割を果たす体制が必要となります。
また、虐待された子どもを保護して、適切なケアを提供する「児童養護施設」の最低基準を改善することも法律のなかで位置づけられています。 さらに、虐待された子どもへの心理的なケアが大切です。精神的な健康への影響だけでなく、その子が親になってから自分の子供を虐待してしまう(世代間の連鎖)が近年、指摘されています。
広岡さんは、心の傷を抱えた母親に対する援助の実践をふりかえって、「自分が何に傷ついていたかに気づくこで・虐待が軽減することもある」と話ます。「人は急に安全な親になる訳ではない。暴力しか体験していなければ、母性や父性は獲得されない」と広岡さん。地域の様々な人との関わりのなかで親子関係を培っていく、そんな子育ての大切さが改めて問われています。
*子どもの権利を改めて見つめ直そう
セミナーでは、カリフォルニア州で臨床ソーシャルワーカーとして、虐待された子どもへの援助に取り組む丸山恭子さんからも報告がありました。「日本では、親との関係に配慮しながら子どもを援助することが多いが、米国では、子どもの福祉を最優先にする専門職が親に嫌われてでも子どもを救い出す」と丸山さん。家庭全体に対するサポートとは別に、〈子ども〉を最優先にした専門職が位置づけられています。
児童虐待防止法を契機に、地域の関係機関が〈子ども〉を中心に連携する体制をつくりあげることが期待されます。また、虐待に傷っいた子どものケアの専門性が実践を通じて確立されるとともに、虐待した親に対する専門的なアプローチが必要です。
子どもの権利を地域で改めて見つめ直すきっかけとしながら、子育てのあり方としてもとめられる視点が大切になるでしょう。
東京都社会福祉協議会の福祉広報より...498 2000年6月号